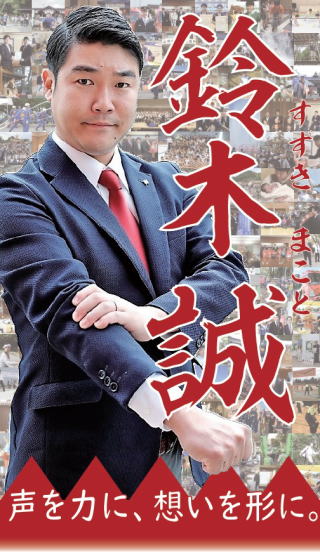- 2019 / 12 / 28
令和元年も早いもので、年末のご挨拶をさせていただく時期に。
今年は平成から令和へと、歴史的な御代替わりでした。
生前退位には驚きもありましたが、これ自体は江戸時代以前の前例に則ったことであり、皇室の長い長い歴史から見れば些細なことと受け止めております。
…残念ながら雨台風をはじめ多くの自然災害が発生してしまいました。天災は致し方ないにせよ、「令和」に込められた願いに反して特に東アジア諸国(中共、南北朝鮮)の暴挙も続く年となってしまいました。
早速関連して、来年予定される習近平氏の国賓待遇来日に一言。中共は、過去に天安門事件からの国際非難脱却のため先々帝陛下の訪中を実現させ、併せて欧米に先駆けた日本からの制裁解除等で人権問題による窮地を脱したことは歴史上明らかになっています。
その先例から、今回もチベット・ウイグル・香港における人権問題、さらには米中貿易戦争の火中にあって、今上陛下を政治的に利用して再び国際的非難を躱そうという意図があるのでは?と懸念しております。
「国家間の友好は良いこと」という目先での意見は勿論うなづけますが、天安門事件で対中融和をして以降、どれほど中共から日本へと利益があったのか?記憶に新しいところだけでも、沖縄分断も視野に、尖閣諸島侵入、不買運動等々、まさに「仇」で返ってきてはいないでしょうか?先日の稲城市議会における議案陳情判断でもそうでしたが、短絡的かつ目先の耳障りが良いことだけでなく、長期的視野でそれが何をもたらすかまで考えなければ、政治に携わるものとして失格だと考えます。
国の専権事項は国がやるべき、ではありますが、政治に携わる以前に一人の民草として、より危機感をもって来年も精進して参ります!
そんなこんなで、今年も残すところ3日ばかり。
何やらインフルエンザ等も流行っている様子。どうか、皆様方におかれましては年末年始も健康にご留意いただき、素晴らしき令和初の新年を迎えられることをお祈り申し上げます。
尚、例年同様ではございますが公職選挙法第147条の2(あいさつ状の禁止)を遵守するため、年賀状をこちらから発送することが叶いません。いただいた方へ答礼の返信になるご無礼を事前にご容赦下さいませ。
以下、令和元年内最後の「いなぎ暮らし」更新です。
---
12月22日(日)、冬至。は神社にて正月準備、配布される「福銭」入れや、初詣のぼり旗設置などが実施され、上平尾地域を主軸に配布する初詣勧誘チラシ関連業務に従事。
そして今月2度目となる平尾団地での火災報(掲示物焼損)、11/26から連続して発生している市内の放火事件には憤りを感じると同時に、犯人の早期逮捕を願いながら自身も警戒に当たって参ります。
 歳末の挨拶回りで柚子をたくさん分けていただき、帰宅後は南瓜食べて、柚子湯で体を温めさせていただきました♪
歳末の挨拶回りで柚子をたくさん分けていただき、帰宅後は南瓜食べて、柚子湯で体を温めさせていただきました♪
23日(月)、一陽来復。これまでなら天長節、天皇誕生日として30年に渡り長らく国民の休日であったわけですが、普通に平日ということで少しばかり拍子抜けながら通常活動。
 夜は、新規消防団員勧誘プロジェクトの一環で、ポスター&ビラに使用する写真をスタジオ撮影。さてさて、どんな写真が上がってくるか楽しみです♪
夜は、新規消防団員勧誘プロジェクトの一環で、ポスター&ビラに使用する写真をスタジオ撮影。さてさて、どんな写真が上がってくるか楽しみです♪
24日(火)は中央公民館等々で各種相談、市役所控室にて諸雑務、他市民相談対応2件。夜は自宅で娘らとミニクリスマス、きちんとサンタクロースなる異国の御仁が丁寧に贈り物を持ってきてくれたそうです(笑)
25日(水)朝方、寒中の古民家公開準備にお邪魔。 土蔵が随分と崩れてきましたが、修復には版築→漆喰は勿論、相当な専門性(とかなりの費用)が必要。今後の同施設方針も改めて考えねば…。
土蔵が随分と崩れてきましたが、修復には版築→漆喰は勿論、相当な専門性(とかなりの費用)が必要。今後の同施設方針も改めて考えねば…。
その後は年内最後の登庁。議会だより用掲載一般質問の書き出しと提出、最後は議会応接室をお借りして市内幼稚園関係者と市子育て部門との意見交換会をセッティングして陪席。「食育の推進」に向けて、また新たな市内子育て事例が完成しそうです♪
夜の市役所→平尾への帰り道によみうりランド通りを選択して大失敗。クリスマス夜のジュエルミネーション近辺なんて大混雑だと分かっていたはずなのに…まんまと大渋滞に巻き込まれてしまいました。
26日(木)は水道橋にて林英臣政経塾戦略部会打ち合わせランチの後、同塾士総会に出席。併せて政治団体『はるか』設立準備総会と、同政経塾の一般社団法人化について。
 全国同志らのプロジェクト推進事例紹介が終わったところで急ぎ退出させていただき、夕方から稲城市消防団歳末特別警戒に出動。市長、議長、災害防止協会会長、団長、自治会長、消防後援会長、女性防火クラブ様ら多くのご来賓の皆様から寒い冬の夜に温かな激励をいただきました!
全国同志らのプロジェクト推進事例紹介が終わったところで急ぎ退出させていただき、夕方から稲城市消防団歳末特別警戒に出動。市長、議長、災害防止協会会長、団長、自治会長、消防後援会長、女性防火クラブ様ら多くのご来賓の皆様から寒い冬の夜に温かな激励をいただきました! 前述の通り、昨今連続している放火魔事件への対応含め、週末予定の歳末特別警戒含めて確りと活動して参ります!
前述の通り、昨今連続している放火魔事件への対応含め、週末予定の歳末特別警戒含めて確りと活動して参ります!
27日(金)、自治会掲示板の整理・貼り替え、御神札引換券配布、入定塚公園不正利用対応施策話し合い、そしてたぶん年内最後であろう市民相談1件対応にて終了。
---
…さてと、年内最後のHP更新もこれにて無事完了!
憂さ晴らしではないですが、今夜はこれから気のおけない大学旧友らと忘年会。幹事曰く「2019年末にふさわしく、19だから、一休に行く!」とよくわからない理屈ではありますが、学生時代を思い出しつつ楽しませていただきます。
本年も当『いなぎ暮らし日記』をご覧いただきまして誠にありがとうございました。皆様、どうぞ良いお年をお迎えくださいませ!
-
- 2019 / 12 / 21
令和元年第4回稲城市議会定例会が閉会。
年内の『公務』と呼ばれるものは終了し、残すは政務活動や地域活動等ばかりです。
以下、取り急ぎ反省を生かして中4日で「いなぎ暮らし」更新です!
---
12月17日(火)、議会運営委員会に始まった本会議最終日。
総務委員長としての委員会報告後、私が最大目標とする『世代循環』のため、話の持って行き方云々や目先の損得ではなく、『子や孫にツケを残さない街づくり』を掲げて陳情討論に立ちました。 朝方は稲城第二小学校の児童たちも併せて満席に近いとても多くの傍聴者がいらしてくださったのですが、残念ながら私の陳情討論の直前の議案討論が終わるやいなや、殆どの方々がお帰りになってしまったので、詳細については下に記します。
朝方は稲城第二小学校の児童たちも併せて満席に近いとても多くの傍聴者がいらしてくださったのですが、残念ながら私の陳情討論の直前の議案討論が終わるやいなや、殆どの方々がお帰りになってしまったので、詳細については下に記します。 (傍聴席の様子。上段は議会冒頭で、下段は閉会寸前。人数がまったく違いますね)
(傍聴席の様子。上段は議会冒頭で、下段は閉会寸前。人数がまったく違いますね)
- 今回は賛否が明確に分かれる議案・陳情が多くあり、討論も活発でしたが『ポピュリズム』『ダブルスタンダード』にも聞こえた他会派の討論内容にはちょっとばかり…。
…で、それら議案討論の度に傍聴人が騒ぎ立て、5度目(私が数え間違えてなければ)までは議長からの口頭注意のみだったのですが、さすがに6度目で議長から当該傍聴人に対して退場が命じられ、実際に退場させられてしまう事態が発生してしまいました。
私が本会議場に出る立場になって以降9年足らずですが、初体験の出来事かと。
※ちなみに、議場ではなく委員会室でなら、委員会終了後に傍聴者の方々から大声で罵詈雑言を浴びせかけられた体験はありますが(苦笑)
◆地方自治法 第130条(傍聴人に対する措置)
傍聴人が公然と可否を表明し、又は騒ぎ立てる等会議を妨害するときは、普通地方公共団体の議会の議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させ、必要がある場合においては、これを当該警察官に引き渡すことができる。
◆稲城市議会傍聴規則 第12条(傍聴人の守るべき事項)
傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
◆ 〃 第16条(違反に対する措置)
法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
 …どこの議員さんが今回退場となった当該人をお誘いしてきたかは、最近開かれていた集会等から凡そ察しはつきますが、もしわざとこのような事を傍聴者にやらせるよう某議員が仕向けたことであったのならば、議会軽視甚だしいことです。そして、そんな陰謀は無かったにせよ、少なくとも自分自身の関係者等であるならば、傍聴側に対して助け船(というか制止)を出すべきかと。
…どこの議員さんが今回退場となった当該人をお誘いしてきたかは、最近開かれていた集会等から凡そ察しはつきますが、もしわざとこのような事を傍聴者にやらせるよう某議員が仕向けたことであったのならば、議会軽視甚だしいことです。そして、そんな陰謀は無かったにせよ、少なくとも自分自身の関係者等であるならば、傍聴側に対して助け船(というか制止)を出すべきかと。
何度も注意と休憩を挟んだのだから、傍聴席に入る際にお渡ししている注意事項は再度読んでいただくとか伝える暇はあったはず…。
まぁ、そんな陰謀=裏工作は、絶対にないと、あってはならないことと信じています!疑うでなく、性善説に則り先ずは人を信じるべきですね。
他、市民相談対応(行政各担当部署と打ち合わせ)等をこなして、深夜の政経塾ZOOM会議もに参加。
議会の詳細は以下の通りです。
12月議会(令和元年第4回稲城市議会定例会)
全38議案の中で審議が分かれたものは以下の11議案。
第61号議案 稲城市手数料条例の一部を改正する条例
第63号議案 稲城市立学校施設使用条例の一部を改正する条例
第64号議案 稲城市立公民館条例の一部を改正する条例
第65号議案 稲城市立公園に設置する稲城市立中央図書館城山体験学習館の管理運営に関する条例の一部を改正する条例
第66号議案 稲城市立i(あい)プラザ条例の一部を改正する条例
第67号議案 稲城市体育施設条例の一部を改正する条例
第68号議案 稲城市学童クラブ設置条例の一部を改正する条例
第69号議案 稲城市地域振興プラザ条例の一部を改正する条例
第71号議案 稲城市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例
第72号議案 稲城市健康プラザ条例の一部を改正する条例
第78号議案 稲城市立公園駐車場の管理等に関する条例の一部を改正する条例
→上記11議案ともに、賛成多数で可決
賛成14名:北浜・中山・坂田・池田・角田・川村・梶浦(新政会)、市瀬・つのじ・佐藤(公明党)、岩佐・榎本(改革稲城の会)、鈴木・中田(起風会)
反対7名:岡田・田島・山岸(日本共産党)、荒井・村上・武田・いそむら(市民クラブ)
上記の11議案の概要は、持続可能な行政運営及び利用者負担の適正化並びに消費税率の引上げへの対応を図る観点から市内施設の使用料や行政サービスの手数料、駐車場料金等を見直すというもの。
こちらについては→鈴木誠の判断理由(令和元年12月議会その1)をご参照ください。
また、陳情が2件ありました。
第8号陳情:幼児教育・保育無償化に伴う給食費についての陳情
第9号陳情:保育園給食食材料費に関する陳情
→上記2陳情ともに、反対多数で不採択
賛成7名:岡田・田島・山岸(日本共産党)、荒井・村上・武田・いそむら(市民クラブ)
反対14名:北浜・中山・坂田・池田・角田・川村・梶浦(新政会)、市瀬・つのじ・佐藤(公明党)、鈴木・中田(起風会)、岩佐・榎本(改革稲城の会)
こちら2陳情の内容は、「認可保育園の給食食材費実費負担分について、市で補助を出して欲しい」というもの。
こちらについても→鈴木誠の判断理由(令和元年12月議会その2)をご参照ください。
18日(水)は前日の議会閉会を受けての報告やら確認やらの1日。他、自治会&自主防災組織関係、翌日の青年会議所事業の準備等雑務、夜は市内一斉防犯パトロールに参加。 昼間は暖かく感じたのに、日が暮れた後は風も強まり体感気温が格段に低下。犯罪件数は漸減ですが、昨今の連続放火事件が心配です…。
昼間は暖かく感じたのに、日が暮れた後は風も強まり体感気温が格段に低下。犯罪件数は漸減ですが、昨今の連続放火事件が心配です…。
19日(木)は午前~午後にかけて、主権者教育事業『みらいく』を稲城市内唯一の公立高校である都立若葉総合高等学校にて開催!

 簡単な模擬選挙を通じつつ、「キミたち若者がもっともっと政治に関心を持って投票に行かないと、より良い未来にはならないぞ!」と心底訴えました。
簡単な模擬選挙を通じつつ、「キミたち若者がもっともっと政治に関心を持って投票に行かないと、より良い未来にはならないぞ!」と心底訴えました。




 最後は18歳になったら選挙に行くよ~という挙手もあり、概ねの内容は伝わったかと。
最後は18歳になったら選挙に行くよ~という挙手もあり、概ねの内容は伝わったかと。
20日(金)は長期総合計画検討特別委員会が開催され、当会派からは中田議員が出席。夕方からは稲城市議会議員互助会主催による恒例の年末忘年会に出席し、今年のラグビーW杯でも話題となった『ノーサイドの精神』にて会派・政党の垣根を超えた交流が図られました。 …私のカラオケも歌い修めです。
…私のカラオケも歌い修めです。
---
…ほんの少々ばかり、昨晩のせいか頭痛で目覚めた本日。
年の暮れも迫り、雑事に追われておりますが、あと十日ばかりの間に本年中にやり残したことがないよう活動して参ります!
-
- 2019 / 12 / 16
『師走(12月)』とは言いますが、今年は自分が主催側であるイベント目白押しであった『霜月(11月)』の方が忙しく感じました。
現在開会中の令和元年最後の稲城市議会定例会(12月議会)も明日で閉会になります。使用料・手数料の改定や、9月議会の再来か?という認可保育園給食費補助陳情2件もありますが、最後の最後まで「バランスを重視」して確りと審議して参ります。
以下、11月初旬~12月中盤迄の丸々一ヶ月半の活動をまとめて報告させていただきます。楽しみにお待ちいただいている有難い稀有な方々には、大変長期間に渡り更新滞りまして申し訳ありませんでした。
もう少し短いスパンで更新できるよう、暫し心がけます。
---
11月5日(火)、市長を含めての会派情報交換会に出席。今回の台風19号を受けての市の対応状況や、今後の方針についてざっくばらんに意見交換することができました。
6日(水)は、準備して翌日朝から始まる都市問題会議へ移動。新百合ヶ丘駅から羽田空港までバス移動の途中、先般の雨台風で脚光を浴びた『新横浜公園』を通りかかりました。 稲城市平尾地域を流れる陣川(神川とも、殆どが暗渠化済み)は鶴見川流域最上流部にあたり、麻生川を通じ鶴見川に合流しています。同流域は上流にダムがあるわけでもなく、密集市街地を流れる、古来より暴れ川としても知られた鶴見川。
稲城市平尾地域を流れる陣川(神川とも、殆どが暗渠化済み)は鶴見川流域最上流部にあたり、麻生川を通じ鶴見川に合流しています。同流域は上流にダムがあるわけでもなく、密集市街地を流れる、古来より暴れ川としても知られた鶴見川。
この対策に設置された多目的遊水地が同・新横浜公園で、併設の日産スタジアムは千本の柱の上に乗っており、洪水時にはスタジアム下に水が入るためラグビーW杯時も水に浮かぶ競技場然としてました。
このような大きな遊水地だけでなく、最上流部に位置する平尾地域内だけでも4つの貯水池(三反田湧水公園の地下神殿、平尾児童公園、平尾山王橋児童公園、平尾谷戸公園)があり、こうした治水施設の集合体が結果として分水嶺で隣接する多摩川と鶴見川の明暗を多少なりとも左右したはず。
ニュータウンの大規模開発に伴い作られた『三沢川放水路』こそ、今回でも本格使用には至らなかった訳ですが、どこまで防災インフラとして行政が取り組み、どこから自然の脅威として住民主体の避難にするのか。多摩川スーパー堤防工区A~Cが市内流域で順調に進んでいたのに、最後の最後で某前政権による『事業仕分け』なるもので、C工区のみ残っている現状…。先日の狩野川水防センター見学でも思ったのですが、水防関連を何とかせねばならんなと再度思う次第。 羽田空港に着くと、なんと断水!塩分濃度が濃いとかなんとか…?
羽田空港に着くと、なんと断水!塩分濃度が濃いとかなんとか…? 鹿児島空港到着後には、ホテルチェックインまで少し時間があったので霊験あらたかな霧島神宮に立ち寄らせていただきました。
鹿児島空港到着後には、ホテルチェックインまで少し時間があったので霊験あらたかな霧島神宮に立ち寄らせていただきました。
7日(木)~8日(金)、第81回全国都市問題会議『防災とコミュニティ』in鹿児島県霧島市に参加。


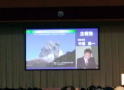 全国市長会会長の立谷・相馬市長による先般の台風19号被害と、別件ですが幼保無償化における「副食費4,500円と国が言及した事」について各担当省庁、大臣らとやり合った話で開会。以下、私なりのまとめ。
全国市長会会長の立谷・相馬市長による先般の台風19号被害と、別件ですが幼保無償化における「副食費4,500円と国が言及した事」について各担当省庁、大臣らとやり合った話で開会。以下、私なりのまとめ。
◆基調講演『鹿児島の歴史から学ぶ防災の知恵』(原口・志學館大教授)
治水の変遷において、氾濫に任せるままにしていた古代(自然堤防)から、中世には霞堤(遊水地)を造り、人口増加により近世以降は連続堤と「脆弱→非脆弱→完全防災」という段階で来た。「災害は起こるもの、完璧には防ぎきれない」という昨今の状況からすると「非脆弱≒レジリエンス」に主軸を戻しても良いのでは?という示唆。一見すると非合理的、非能率的な薩摩藩独特の『門割制度』も共助の防災農法として優れ『うったちが早い』(取り掛かり、立ち直りが早い)という『早い人≒隼人』気質に繋がっている等かなり興味深い内容でした!
…ただ、早口&薩摩藩の政策(郷中制度とか)や姶良火山等の地学的基礎知識(溶結凝灰岩質、シラス台地とか)について幸いにも歴史オタ&地学マニアの私としては超得意分野でした。
◆主報告『霧島市の防災の取組~火山防災~』(中重・霧島市長)
平成23年、約300年振りに霧島山(新燃岳)が噴火して以来最近までの状況と対応。死者こそなかったものの「空振」による家屋等のガラス割れ、降灰による農業被害、正確な情報発信が出来なかったことによる観光客激減ダメージがあった。住民に対しては「新燃岳安全対策マップ」の作成配布や、噴火避難計画の策定、避難行動要支援者・独居高齢者らの把握。農業へは洗浄用水の確保と農業用水の保全、火山灰浚渫。観光、風評被害に関しては詳細な警戒範囲と距離の情報発信、火山防災情報を掲載した観光リーフレットの配布等を実施。『環霧島会議』を通じた相互応援協定締結等で地域団体、住民の相互協力を推進中。
◆一般報告『災害とコミュニティ:地域から地域防災力強化への答えを出すために』(田中・尚絅学院大教授)
日本には完全に安全な住処が無い、桜島の目の前に50万人都市の鹿児島市、積雪数メートルになるところに30万人都市の青森市。こんなのは世界で日本だけで、日本人は災害と付き合って生きているといえる。ただ、住民は自治体に、自治体は国に防災依存しているのがこれまでの流れ、阪神淡路大震災から風向きは変わったが自助共助のためコミュニティが自主防災の要。防災に関係なく生活コミュニティ(自治会だけでなく地の各種団体等による重層的なもの)作りが必須だが、上意下達、行政主導では作り得ない(行政側は「公平性の原則」が足枷になる)。『ゆるい全市的な基準』『その地区の実情に合わせた個別的対応』が肝要で、一律的に中央に頼らず「それぞれの地域毎に住民が関心あるテーマを軸に協働し答えを出しながらコミュニティを醸成すること」と「その主軸となるキーパーソンの発掘」が近道。
◆一般報告『平成30年7月豪雨災害における広島市の対応と取組について』(松井・広島市長)
近年、広島市内では台風や線状降水帯によるバックビルディング現象などで幾度かの土砂崩れが起きた。その後、体制を一新し危機管理室に役所の全機能を集約し、警戒・対策手順の整備、防災情報共有システム構築を実施。復旧にあたっては例外的対応を率先して行い、罹災証明発行を迅速化するために税務職員は被災対応にあたらせず本来業務に専念させた。災害は完全には防げない、いざという時のさらに後どのように地域を蘇生させるかを地域住民(特に次世代の防災リーダー養成と並行)と一緒に考えておくこと。正常性バイアスの排除、オオカミ少年になってでも最善を尽くす。災害は検証し、記録を残し、継承する。
◆一般報告『火山災害と防災』(中田・防災科学技術研究所火山研究推進センター長)
雲仙普賢岳の噴火等含めても、実は日本の火山は中噴火まではありこそすれ巨大噴火は300年、大噴火100年無いという静かすぎる状況にあり、そろそろ注意が必要。他の火山国と違い、日本は縦割り行政の弊害で機関がバラバラ。せめて研究予測部門と発信報道部門だけでもより緊密な連携が急務。研究者・行政・マスメディアの三者が住民を支えるべき。防災と観光は相反すると言われがちだが、「防災を観光のネタにする」というのも1つの手段。特にジオパークという仕組みはその可能性が大きく秘められている。火山がもたらす温泉や景観等の恩恵を活用すると同時に、発生頻度が低いが大惨事に繋がることを認識し、郷土愛を柱に地域の各種団体・企業や構成員全員が関わる『長続きするジオパーク火山防災(SDGs風)』を目指すべき。伊豆ジオパークにほぼ毎年通う身としては、今後ちょっと注視してみようと思います。
◆パネルディスカッション『防災とコミュニティ』(コーディネーター:田中・追手門学院大教授、パネリスト:大矢根・専修大教授、磯打・香川大特命准教授、持留・自治公民館長、豊岡・静岡県三島市長、神出・和歌山県海南市長)
文化伝統に紐づく人と人のつながりが希薄な都市部。災害が激化するのに対して、災害リスクの複雑化・不可視化・個人化(誰がどこに住んで何をしているか分からないから安否確認も出来ない)が進んでいる。防災の主体者は誰なのか、地域・行政が連携統合したコミュニティー形成が必須である。
防災力とは『レジリエンス(逆境に対し克服していく力)』であるべきで、事前復興と地区防災計画を主体にすべき。生活に組み込まれた防災として、誰が何をするのかというところまで踏み込む必要がある。こうした際にとても重要な防災名簿等作成時によく突かれる「個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)」であるが、同法23条の二では「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」は「本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供して」も良いとなっている。法律はよく読み込むべき。在るモノ・居るヒトを活用する事例として、都立両国高校が実施するマンション安否確認学習などがある。
行政と住民の信頼関係醸成、自助共助公助の概念(自分はここまで、こっからは誰がやってくれるだろう)を取っ払う、身近に日常からあるモノとヒトを連携させることが重要であると結論づけられました。
他、インバウンド隆盛における外国人観光客の避難、フェイクニュース対応、自主防災組織見直しなど『防災の主流化促進』により各々が得意分野の力を発揮するべき。富士山のお膝元・三島市では、ジュニアレスキュー隊やチャリンコ隊など若年層が出来ることを活用したり、市職員でオフロードバイク隊を結成するなどの取り組みをしている事。南海トラフ津波による大被害が想定される海南市は、水防対策や高台への市役所移転を行い、市民一成防災訓練には市民の半数である2万人も参加するという比較的防災意識が高い状況。行政だけで行えることは限界があり、共助が大切。市職員と地域の信頼関係構築に努めている。等の事例紹介がありました。
…2日間に渡ってみっちりと受けた同研修内容を稲城市政、特に防災施策に活かすべく、早速12月5日に登壇した一般質問に組み込みました!(詳細は是非ともこちらの一般質問動画をご覧ください)
 ちなみに会議場外では「鈴懸馬踊り」なるものが催されておりました。そして、テレビでもおなじみのアヒル隊長はなんと霧島温泉大使なんだとか!
ちなみに会議場外では「鈴懸馬踊り」なるものが催されておりました。そして、テレビでもおなじみのアヒル隊長はなんと霧島温泉大使なんだとか!
9日(土)は早朝6時台から会派起風会の同志・中田中氏が全精力を注ぐ、若葉台まちびらき20周年『わかばのマルシェ』開催準備のお手伝い(テント張り等)。
 その後は子供食堂クッチィナいなぎ@城山文化センターを開催。
その後は子供食堂クッチィナいなぎ@城山文化センターを開催。

 『秋の味覚!ほうとう&栗きんとん』を目指して、薄力粉+強力粉から作る麺、芋を蒸かすところから始まる栗きんとんに、子供達も楽しんでくれたようです♪
『秋の味覚!ほうとう&栗きんとん』を目指して、薄力粉+強力粉から作る麺、芋を蒸かすところから始まる栗きんとんに、子供達も楽しんでくれたようです♪
夕方は、行政でお世話になっている方のご尊父様葬儀に弔問させていただきました。夜は地元・平尾にて後援会青年部長との会合、少し遅刻してしまいましたが閉店時間まで楽しい一時を過ごせました。
10日(日)も早朝より準備(フリーマーケット店舗区角割)に始まり、第7回・平尾まつり@ふれんど平尾&第三文化センターを開催。

 色んな体験、催し物、物販・飲食が揃い、天気も良かったこともあり大盛況でした!
色んな体験、催し物、物販・飲食が揃い、天気も良かったこともあり大盛況でした!
本来は消防団体力錬成事業の日だったため、夕方からは「火災繁忙期より事前に」が習わしの分団忘年会に出席。今年は平尾地域と、隣接する麻生区でも火災が多かったことを受け、各自意見交換も出来ました。
11日(月)午前中は東京都三市収益事業組合全員協議会&議会(決算認定)を東京自治会館にて、民間力活用(江戸川競艇駐車場利活用)について私も仔細質疑させていただき今後の継続を要望しました。
午後は稲城市役所防犯&防災訓練に参加。
 私も現場を目の当たりにした市役所放火事件から早4年、「御礼参り」が危惧され更なる対策強化が求められる中での実戦的訓練でした!
私も現場を目の当たりにした市役所放火事件から早4年、「御礼参り」が危惧され更なる対策強化が求められる中での実戦的訓練でした!

 歳末の挨拶回りで柚子をたくさん分けていただき、帰宅後は南瓜食べて、柚子湯で体を温めさせていただきました♪
歳末の挨拶回りで柚子をたくさん分けていただき、帰宅後は南瓜食べて、柚子湯で体を温めさせていただきました♪
 夜は、新規消防団員勧誘プロジェクトの一環で、ポスター&ビラに使用する写真をスタジオ撮影。さてさて、どんな写真が上がってくるか楽しみです♪
夜は、新規消防団員勧誘プロジェクトの一環で、ポスター&ビラに使用する写真をスタジオ撮影。さてさて、どんな写真が上がってくるか楽しみです♪ 土蔵が随分と崩れてきましたが、修復には版築→漆喰は勿論、相当な専門性(とかなりの費用)が必要。今後の同施設方針も改めて考えねば…。
土蔵が随分と崩れてきましたが、修復には版築→漆喰は勿論、相当な専門性(とかなりの費用)が必要。今後の同施設方針も改めて考えねば…。
 全国同志らのプロジェクト推進事例紹介が終わったところで急ぎ退出させていただき、夕方から稲城市消防団歳末特別警戒に出動。市長、議長、災害防止協会会長、団長、自治会長、消防後援会長、女性防火クラブ様ら多くのご来賓の皆様から寒い冬の夜に温かな激励をいただきました!
全国同志らのプロジェクト推進事例紹介が終わったところで急ぎ退出させていただき、夕方から稲城市消防団歳末特別警戒に出動。市長、議長、災害防止協会会長、団長、自治会長、消防後援会長、女性防火クラブ様ら多くのご来賓の皆様から寒い冬の夜に温かな激励をいただきました! 前述の通り、昨今連続している放火魔事件への対応含め、週末予定の歳末特別警戒含めて確りと活動して参ります!
前述の通り、昨今連続している放火魔事件への対応含め、週末予定の歳末特別警戒含めて確りと活動して参ります! 朝方は稲城第二小学校の児童たちも併せて満席に近いとても多くの傍聴者がいらしてくださったのですが、残念ながら私の陳情討論の直前の議案討論が終わるやいなや、殆どの方々がお帰りになってしまったので、詳細については下に記します。
朝方は稲城第二小学校の児童たちも併せて満席に近いとても多くの傍聴者がいらしてくださったのですが、残念ながら私の陳情討論の直前の議案討論が終わるやいなや、殆どの方々がお帰りになってしまったので、詳細については下に記します。 (傍聴席の様子。上段は議会冒頭で、下段は閉会寸前。人数がまったく違いますね)
(傍聴席の様子。上段は議会冒頭で、下段は閉会寸前。人数がまったく違いますね)
 …どこの議員さんが今回退場となった当該人をお誘いしてきたかは、最近開かれていた集会等から凡そ察しはつきますが、もしわざとこのような事を傍聴者にやらせるよう某議員が仕向けたことであったのならば、議会軽視甚だしいことです。そして、そんな陰謀は無かったにせよ、少なくとも自分自身の関係者等であるならば、傍聴側に対して助け船(というか制止)を出すべきかと。
…どこの議員さんが今回退場となった当該人をお誘いしてきたかは、最近開かれていた集会等から凡そ察しはつきますが、もしわざとこのような事を傍聴者にやらせるよう某議員が仕向けたことであったのならば、議会軽視甚だしいことです。そして、そんな陰謀は無かったにせよ、少なくとも自分自身の関係者等であるならば、傍聴側に対して助け船(というか制止)を出すべきかと。 昼間は暖かく感じたのに、日が暮れた後は風も強まり体感気温が格段に低下。犯罪件数は漸減ですが、昨今の連続放火事件が心配です…。
昼間は暖かく感じたのに、日が暮れた後は風も強まり体感気温が格段に低下。犯罪件数は漸減ですが、昨今の連続放火事件が心配です…。
 簡単な模擬選挙を通じつつ、「キミたち若者がもっともっと政治に関心を持って投票に行かないと、より良い未来にはならないぞ!」と心底訴えました。
簡単な模擬選挙を通じつつ、「キミたち若者がもっともっと政治に関心を持って投票に行かないと、より良い未来にはならないぞ!」と心底訴えました。




 最後は18歳になったら選挙に行くよ~という挙手もあり、概ねの内容は伝わったかと。
最後は18歳になったら選挙に行くよ~という挙手もあり、概ねの内容は伝わったかと。 …私のカラオケも歌い修めです。
…私のカラオケも歌い修めです。 稲城市平尾地域を流れる陣川(神川とも、殆どが暗渠化済み)は鶴見川流域最上流部にあたり、麻生川を通じ鶴見川に合流しています。同流域は上流にダムがあるわけでもなく、密集市街地を流れる、古来より暴れ川としても知られた鶴見川。
稲城市平尾地域を流れる陣川(神川とも、殆どが暗渠化済み)は鶴見川流域最上流部にあたり、麻生川を通じ鶴見川に合流しています。同流域は上流にダムがあるわけでもなく、密集市街地を流れる、古来より暴れ川としても知られた鶴見川。 羽田空港に着くと、なんと断水!塩分濃度が濃いとかなんとか…?
羽田空港に着くと、なんと断水!塩分濃度が濃いとかなんとか…? 鹿児島空港到着後には、ホテルチェックインまで少し時間があったので霊験あらたかな霧島神宮に立ち寄らせていただきました。
鹿児島空港到着後には、ホテルチェックインまで少し時間があったので霊験あらたかな霧島神宮に立ち寄らせていただきました。

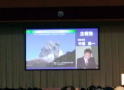 全国市長会会長の立谷・相馬市長による先般の台風19号被害と、別件ですが幼保無償化における「副食費4,500円と国が言及した事」について各担当省庁、大臣らとやり合った話で開会。以下、私なりのまとめ。
全国市長会会長の立谷・相馬市長による先般の台風19号被害と、別件ですが幼保無償化における「副食費4,500円と国が言及した事」について各担当省庁、大臣らとやり合った話で開会。以下、私なりのまとめ。
 ちなみに会議場外では「鈴懸馬踊り」なるものが催されておりました。そして、テレビでもおなじみのアヒル隊長はなんと霧島温泉大使なんだとか!
ちなみに会議場外では「鈴懸馬踊り」なるものが催されておりました。そして、テレビでもおなじみのアヒル隊長はなんと霧島温泉大使なんだとか!
 その後は子供食堂クッチィナいなぎ@城山文化センターを開催。
その後は子供食堂クッチィナいなぎ@城山文化センターを開催。

 『秋の味覚!ほうとう&栗きんとん』を目指して、薄力粉+強力粉から作る麺、芋を蒸かすところから始まる栗きんとんに、子供達も楽しんでくれたようです♪
『秋の味覚!ほうとう&栗きんとん』を目指して、薄力粉+強力粉から作る麺、芋を蒸かすところから始まる栗きんとんに、子供達も楽しんでくれたようです♪

 色んな体験、催し物、物販・飲食が揃い、天気も良かったこともあり大盛況でした!
色んな体験、催し物、物販・飲食が揃い、天気も良かったこともあり大盛況でした!
 私も現場を目の当たりにした市役所放火事件から早4年、「御礼参り」が危惧され更なる対策強化が求められる中での実戦的訓練でした!
私も現場を目の当たりにした市役所放火事件から早4年、「御礼参り」が危惧され更なる対策強化が求められる中での実戦的訓練でした!